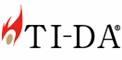地中に埋まっていたシーサー

はいさい!
しまんちゅ工房のあらかきです。
今日は、村落獅子のご紹介。
なっなんと!
地中に埋まっていた村落獅子だそうです。
沖縄は1945年
4人に一人がなくなるという、とんでもない地上戦があり、
その時
おおくの文化財が失われましたが
こうした元々設置されていた村落獅子も戦火のあと、
急速のインフラ整備にともなって行方がわからなくなることが多かったようです。
今日ご紹介する村落獅子もその戦火に巻き込まれ
行方不明になっていたそうですが・・・。
ある記事では道路工事
ある本では水道工事で!と様々ですが、
地中に埋まっていたのを発見していまの位置に設置されたようです。
良かった~~(^^)
沖縄の村落獅子は、石灰岩を使用したモノが多くて
風化が著しいモノが多いのですが、
表情もなんとなく穏やかに見える獅子が多いです。

場所は、与那原町の東の位置。
北のシーサーと呼ばれているという記事を読んだのですが、
どうして北なのか?わかりませんでした。
ただ与那原町の地図からいうと一番東に位置する村落獅子。
ただ
与那原町はさらに東に当添えという地域があります。
本来なら当添えが隣の町との境目になるので
町の一番東は当添えとなります。
ただ!与那原の歴史を知っていると
なぜ
当添えじゃなくて板良敷なのか?とすぐ分かる事なのですが
ヒントは「人口」です。
元々
与那原町は、大里村から別れた町で
町としては商業や交通の要として栄えてきた歴史があります。
それに伴って人口も増えてきた。
さらに言うと
町には与那原大綱曳という500年以上も歴史がある祭りがあります。
その祭りの中心にいた地域があり
当添えや、僕達がいる上与那原地区は実はこの綱曳に参加出来なかった歴史があります。
そうした事から
旧6区と呼ばれる行政区域があり
戦後
先輩たちがそういった古い伝統はなくそう!
町全体で盛り上がる町にしよう!と改革をしてきたのでした。
その名残が
当添えという町の外れになるはずの地域に村落獅子が設置されたのではなく
旧6区と呼ばれる板良敷に鎮座する。
・・・。
と僕は解釈していますがわかりません笑
というのも
ここまでの話は、村落獅子としての見方をしていますが
こう書いていて
いや単純に与那原という地域を守護する村落獅子ではなく地域獅子なのでは?という
解釈もあるなーと・・・。
むしろこっちの解釈の方が強い!
という事でさらに勉強していきたいと思います!!!
この写真では分かりにくいのですが
シーサーは向いている方角が、西で
そこには雨ごい森と呼ばれる小さな山があります。
富盛のシーサーと似ていますね。
山火事に対応したのでしょうか?
そういった文献はないのですが
おそらくそうだと思います。
または
山から海へを流れる大きな気を和らげる風水学なのかもしれません。
いや・・・。
考えてみたら
地中から発見されて戦後
設置されたのですから
交通安全!!!
かもしれません(^^)
いずれにせよ
当時設置された人の想いは地域の平安を願っていたのだと思います。
県道331号線を見守る獅子
与那原町は板良敷の村落獅子でした。
これで二体目
残り!5体!
南・東と来たので
たまたまですが、
自分がいる地域から反対時計回りできたので
次回は、与那原町で一番北にいる村落獅子をご紹介したいと思います(^^)
今日も最後までお付き合い頂いていっぺーいっぺーにふぇーでーびる(^^)
またやーさい(^^)
関連記事